No.130
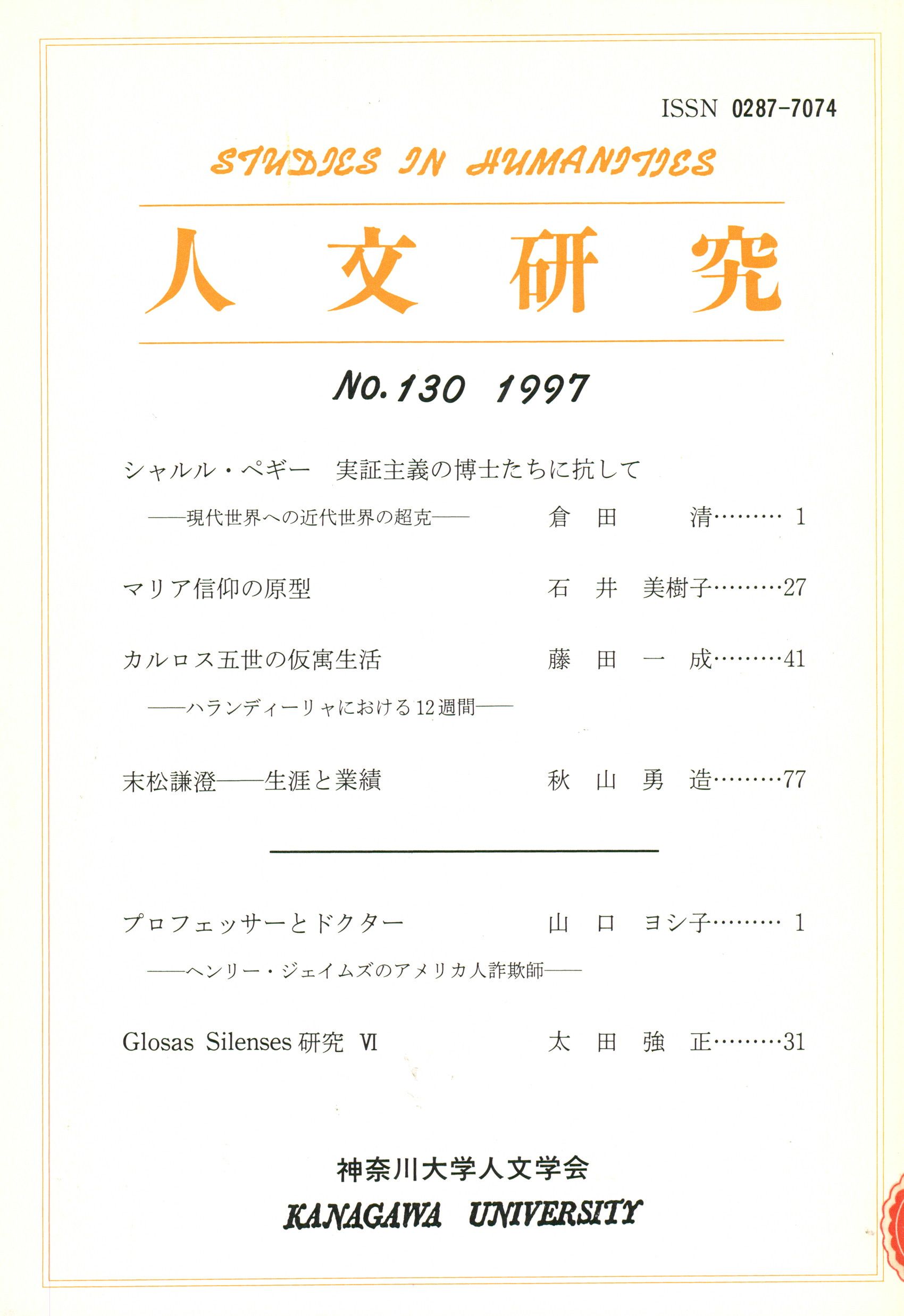
- シャルル・ペギー 実証主義の博士たちに抗して
-現代世界への近代世界の超克-倉田 清 - マリア信仰の原型石井 美樹子
- カルロス五世の仮寓生活
-ハランディーリャにおける12週間-藤田 一成 - 末松謙澄-生涯と業績秋山 勇造
- プロフェッサーとドクター
-ヘンリー・ジェイムズのアメリカ人詐欺師-山口 ヨシ子 - Glosas Silenses研究VI太田 強正
No.129
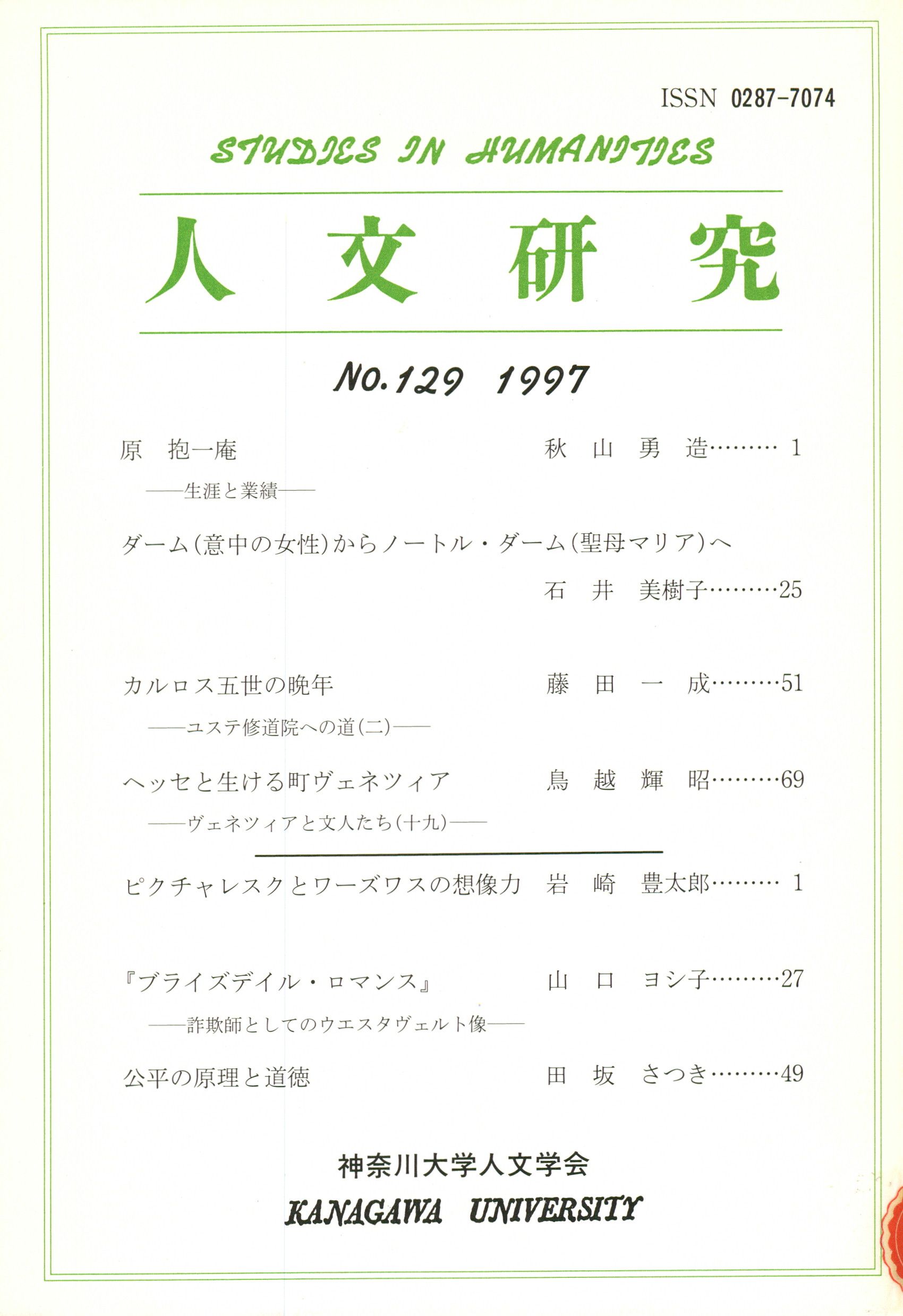
- 原 抱一庵-生涯と業績-秋山 勇造
- ダーム(意中の女性)からノートル・ダーム(聖母マリア)へ 石井 美樹子
- カルロス五世の晩年-ユステ修道院への道(二)-藤田 一成
- ヘッセと生ける町ヴェネツィア-ヴェネツィアと文人たち(十九)-鳥越 輝昭
- ピクチャレスクとワーズワスの想像力岩崎 豊太郎
- 『ブライズデイル・ロマンス』-詐欺師としてのウエスタヴェルト像-山口 ヨシ子
- 公平の原理と道徳田坂 さつき
No.128
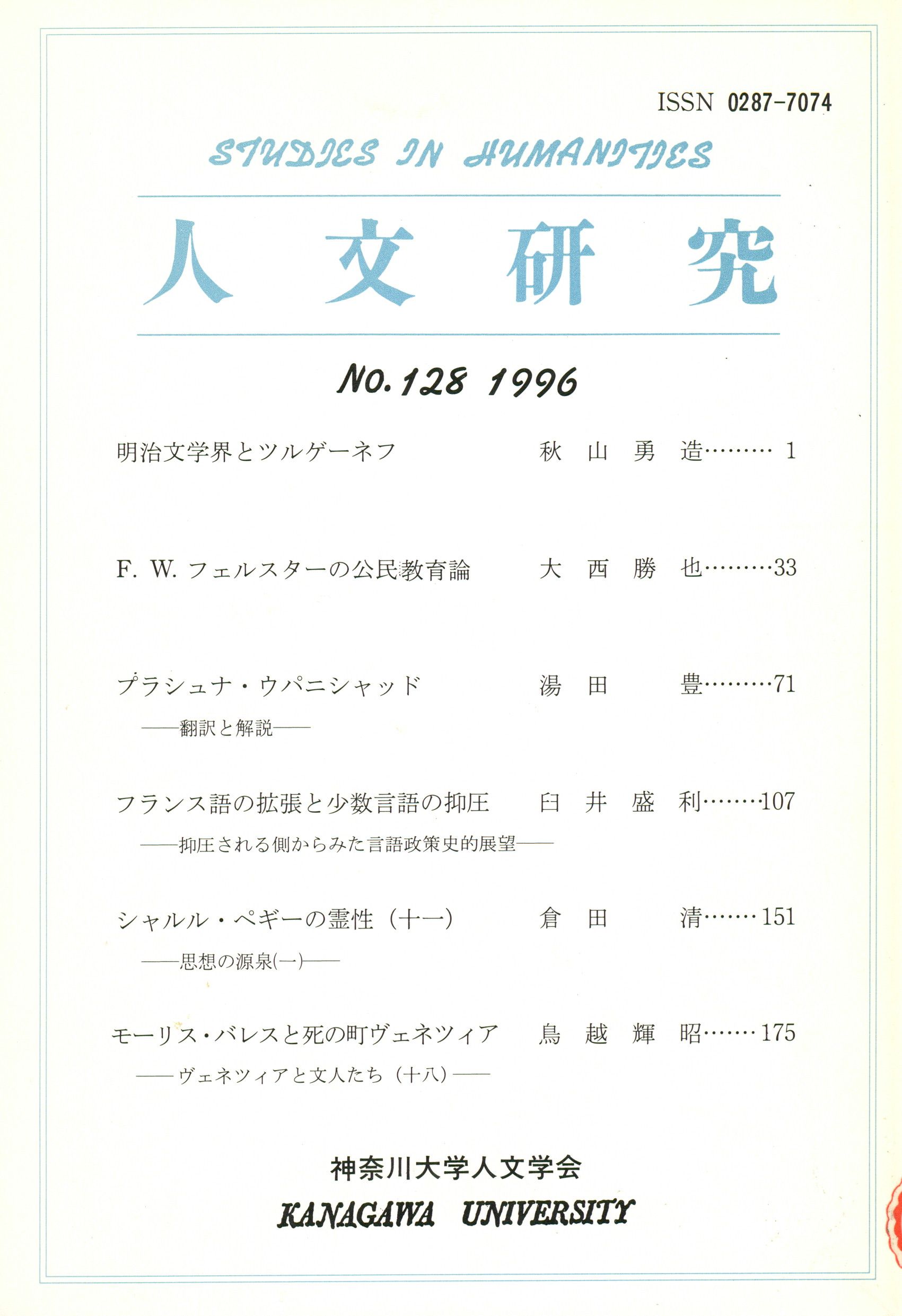
- 明治文学界とツルゲーネフ秋山 勇造
- F.W.フェルスターの公民教育論大西 勝也
- プラシュナ・ウパニシャッド-翻訳と解説-湯田 豊
- フランス語の拡張と少数言語の抑圧
-抑圧される側からみた言語政策史的展望-臼井 盛利 - シャルル・ペギーの霊性(十一)-思想の源泉(一)-倉田 清
- モーリス・バレスと死の町ヴェネツィア
-ヴェネツィアと文人たち(十八)-鳥越 輝昭
No.127
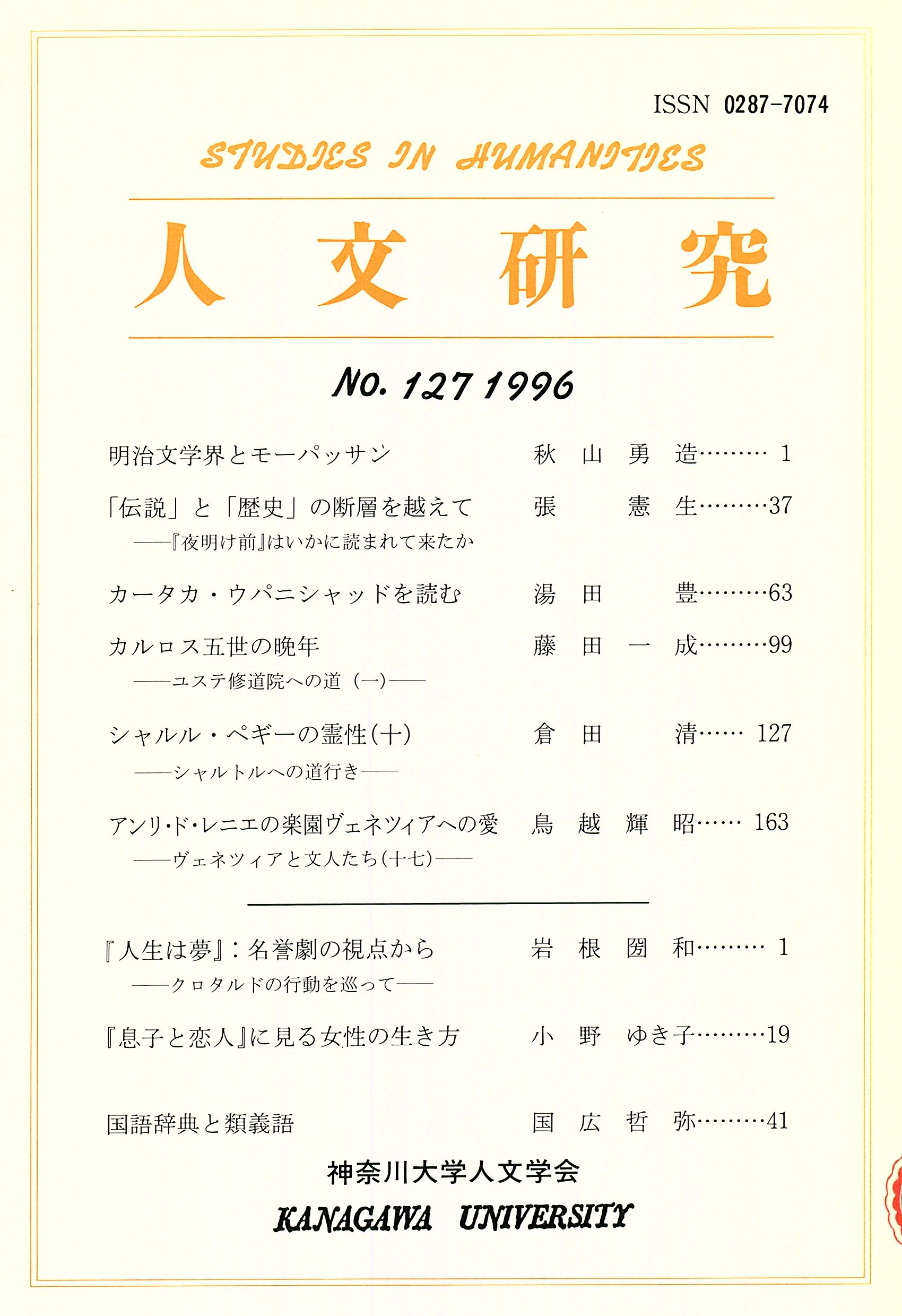
- 明治文学界とモーパッサン秋山 勇造
- 「伝説」と「歴史」の断層を越えて-『夜明け前』はいかに読まれて来たか張 憲生
- カータカ・ウパニシャッドを読む湯田 豊
- カルロス五世の晩年-ユステ修道院への道(一)- 藤田 一成
- シャルル・ペギーの霊性(十)-シャルトルへの道行き-倉田 清
- アンリ・ド・レニエの楽園ヴェネツィアへの愛
-ヴェネツィアと文人たち(十七)-鳥越 輝昭 - 『人生は夢』:名誉劇の視点から
-クロタルドの行動を巡って-岩根 圀和 - 『息子と恋人』に見る女性の生き方小野 ゆき子
- 国語辞典と類義語国広 哲弥
No.126
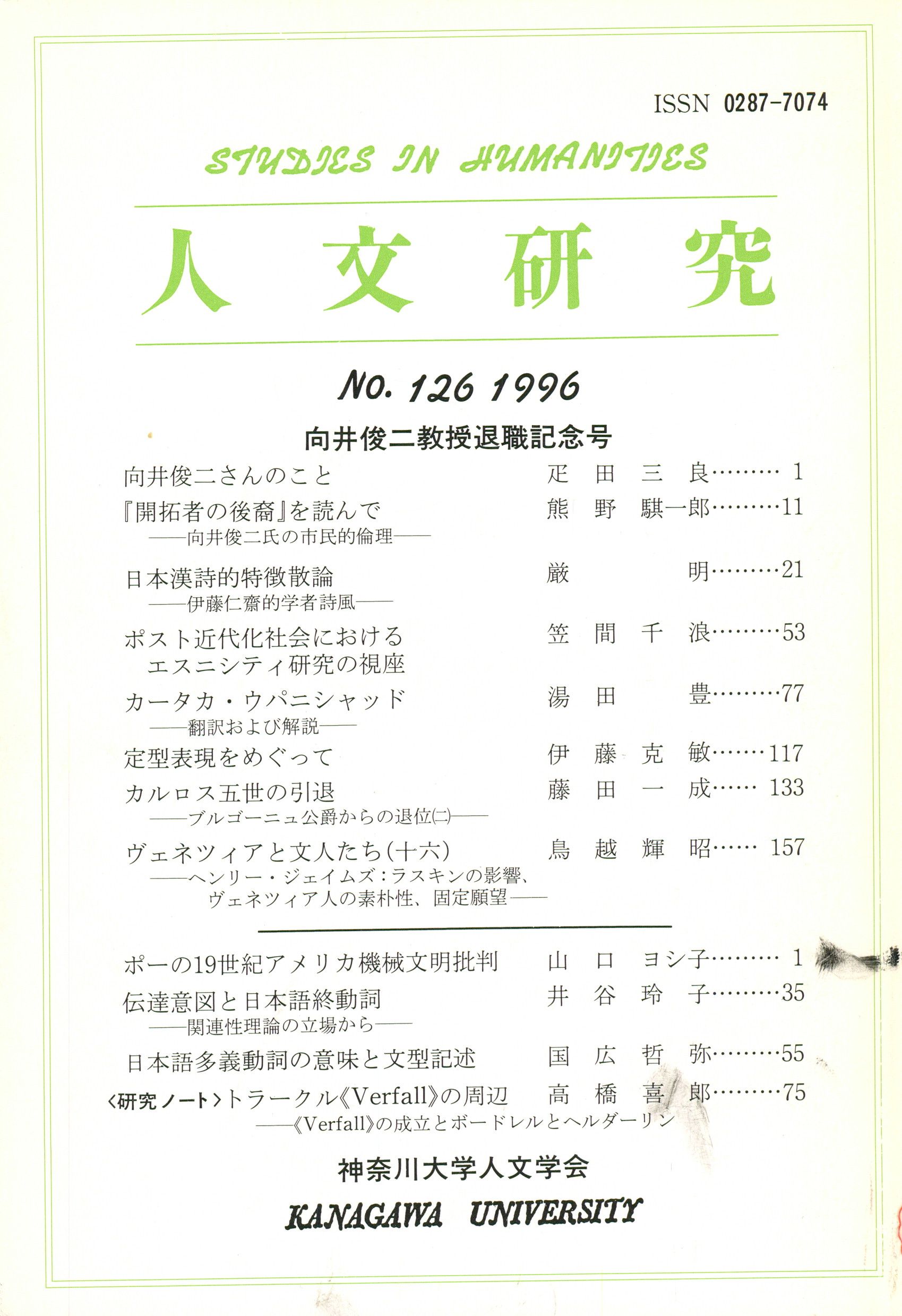
- 向井俊二教授
- 向井俊二さんのこと疋田 三良
- 『開拓者の後裔』を読んで-向井俊二氏の市民的倫理-熊野 騏一郎
- 日本漢詩的特徴散論-伊藤仁斎的学者詩風-厳 明
- ポスト近代化社会におけるエスニシティ研究の視座笠間 千浪
- カータカ・ウパニシャッド-翻訳および解説-湯田 豊
- 定型表現をめぐって伊藤 克敏
- カルロス五世の引退-ブルゴーニュ公爵からの退位(二)-藤田 一成
- ヴェネツィアと文人たち(十六)
-ヘンリー・ジェイムズ:ラスキンの影響、ヴェネツィア人の素朴性、固定願望-鳥越 輝昭 - ポーの19世紀アメリカ機械文明批判山口 ヨシ子
- 伝達意図と日本語終動詞-関連性理論の立場から-井谷 玲子
- 日本語多義動詞の意味と文型記述国広 哲弥
- <研究ノート>トラークル≪Verfall≫の周辺
-≪Verfall≫の成立とボードレルとヘルダーリン高橋 喜郎
No.125
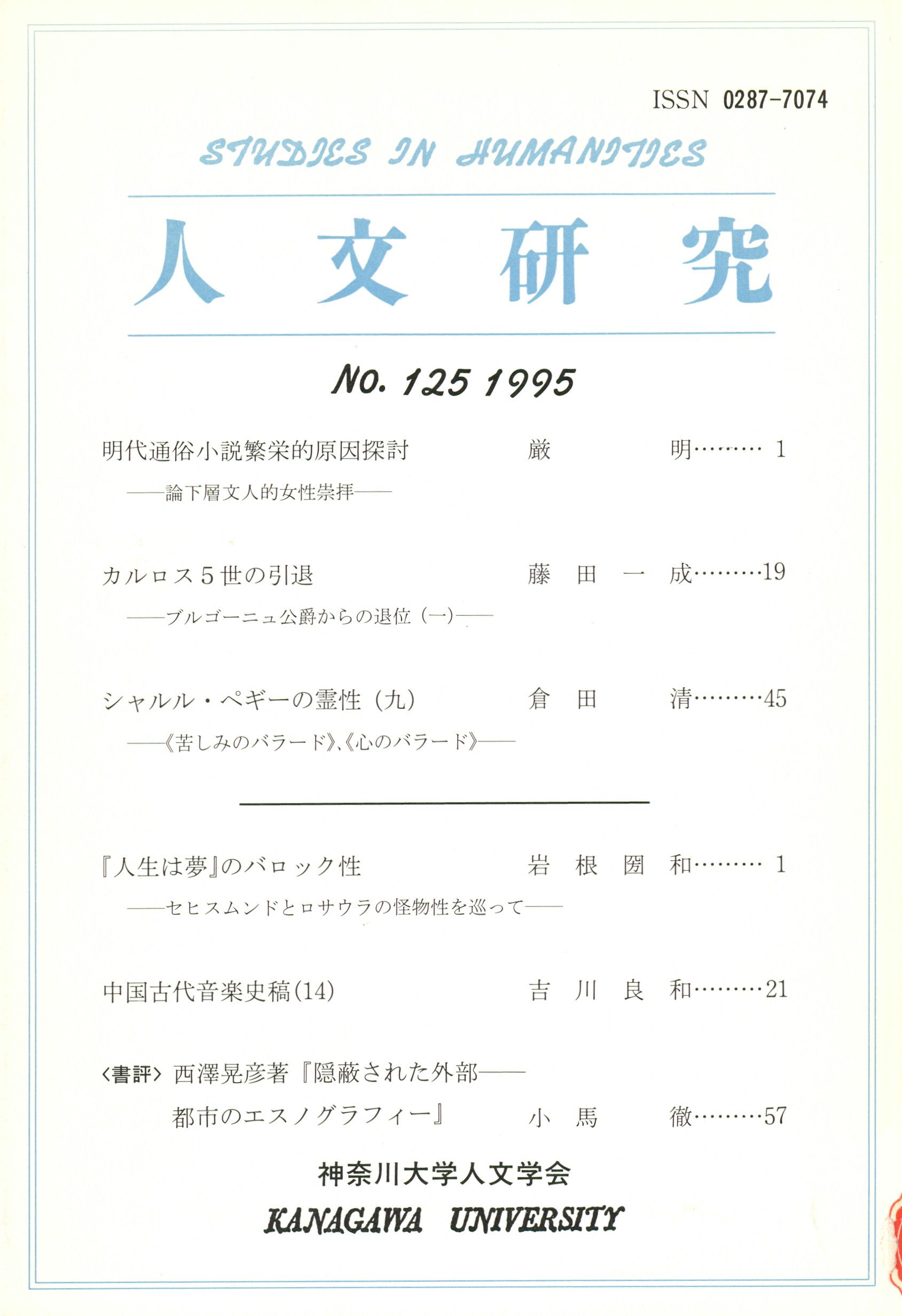
- 明代通俗小説繁栄的原因探討-論下層文人的女性崇拝-厳 明
- カルロス5世の引退-ブルゴーニュ公爵からの退位(一)-藤田 一成
- シャルル・ペギーの霊性(九) -《苦しみのバラード》、《心のバラード》-倉田 清
- 『人生は夢』のバロック性-セヒスムンドとロサウラの怪物性を巡って-岩根 圀和
- 中国古代音楽史稿(14)吉川 良和
- <書評>西澤晃彦著『隠蔽された外部-都市のエスノグラフィー』小馬 徹
No.124
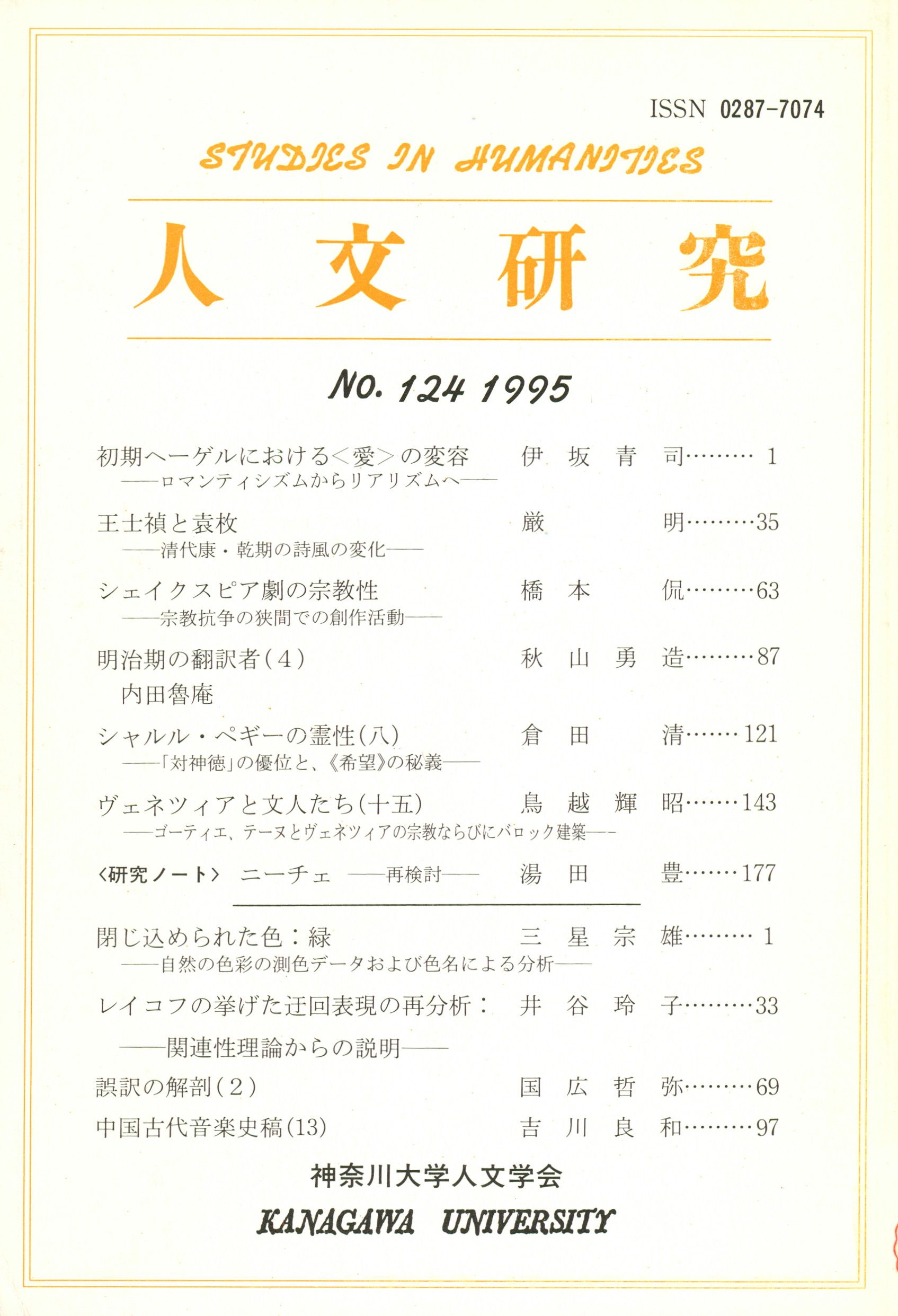
- 初期ヘーゲルにおける<愛>の変容-ロマンティシズムからリアリズムへ-伊坂 青司
- 王士禎と袁枚-清代康・乾期の詩風の変化-厳 明
- シェイクスピア劇の宗教性-宗教抗争の狭間での創作活動-橋本 侃
- 明治期の翻訳者(4) 内田魯庵秋山 勇造
- シャルル・ペギーの霊性(八)-「対神徳」の優位と、≪希望≫の秘義- 倉田 清
- ヴェネツィアと文人たち(十五)
-ゴーティエ、テーヌとヴェネツィアの宗教ならびにバロック建築-鳥越 輝昭 - <研究ノート>ニーチェ-再検討-湯田 豊
- 閉じ込められた色:緑-自然の色彩の測色データおよび色名による分析-三星 宗雄
- レイコフの挙げた迂回表現の再分析:-関連性理論からの説明-井谷 玲子
- 誤訳の解剖(2)国広 哲弥
- 中国古代音楽史稿(13)吉川 良和
No.123
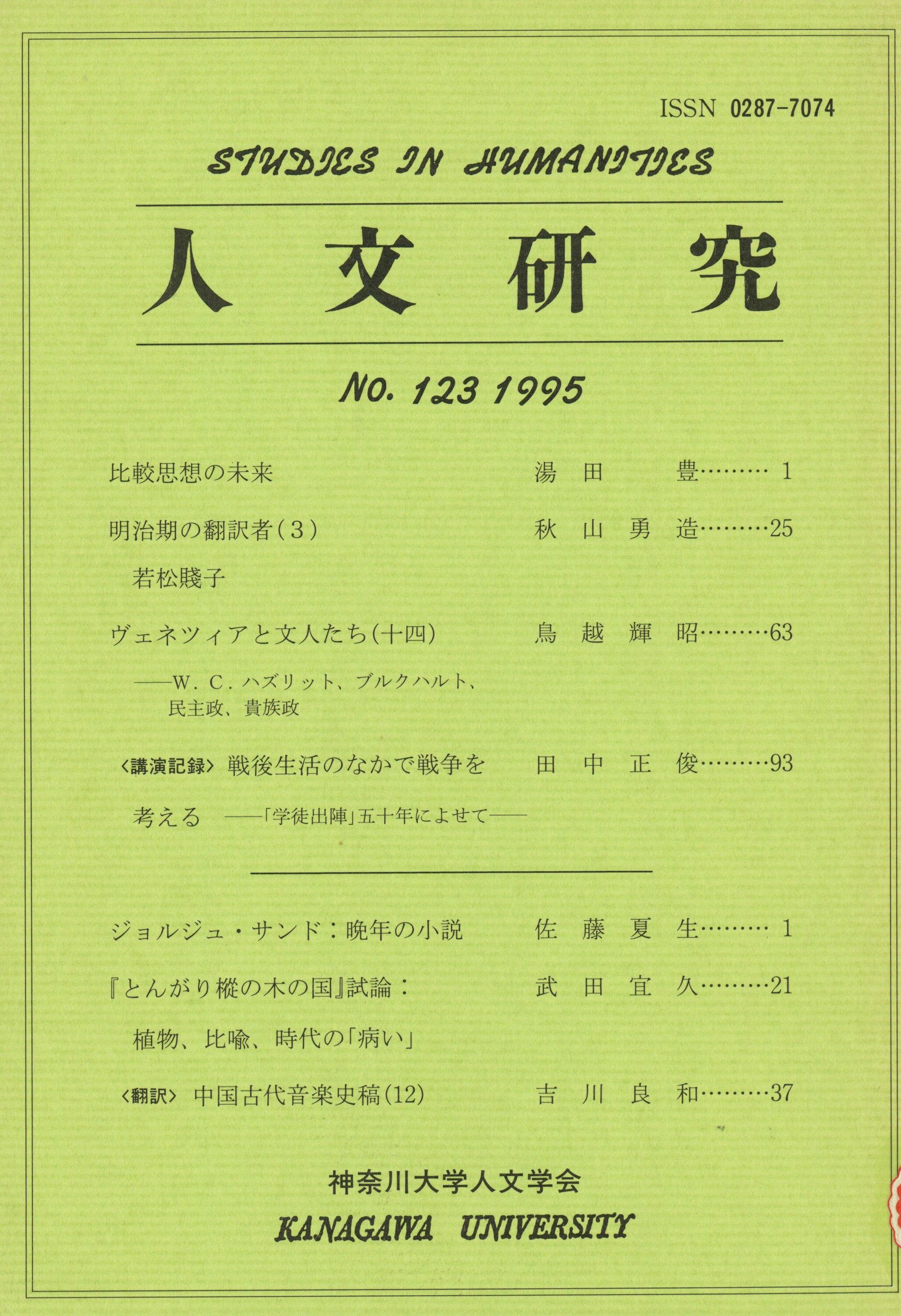
- 比較思想の未来湯田 豊
- 明治期の翻訳者(3)若松賤子秋山 勇造
- ヴェネツィアと文人たち(十四)
-W.C.ハズリット、ブルクハルト、民主政、貴族政-鳥越 輝昭 - <講演記録>戦後生活のなかで戦争を考える-「学徒出陣」五十年によせて-田中 正俊
- ジョルジュ・サンド:晩年の小説佐藤 夏生
- 『とんがり樅の木の国』試論:植物、比喩、時代の「病い」 武田 宜久
- <翻訳>中国古代音楽史稿(12)吉川 良和
No.122
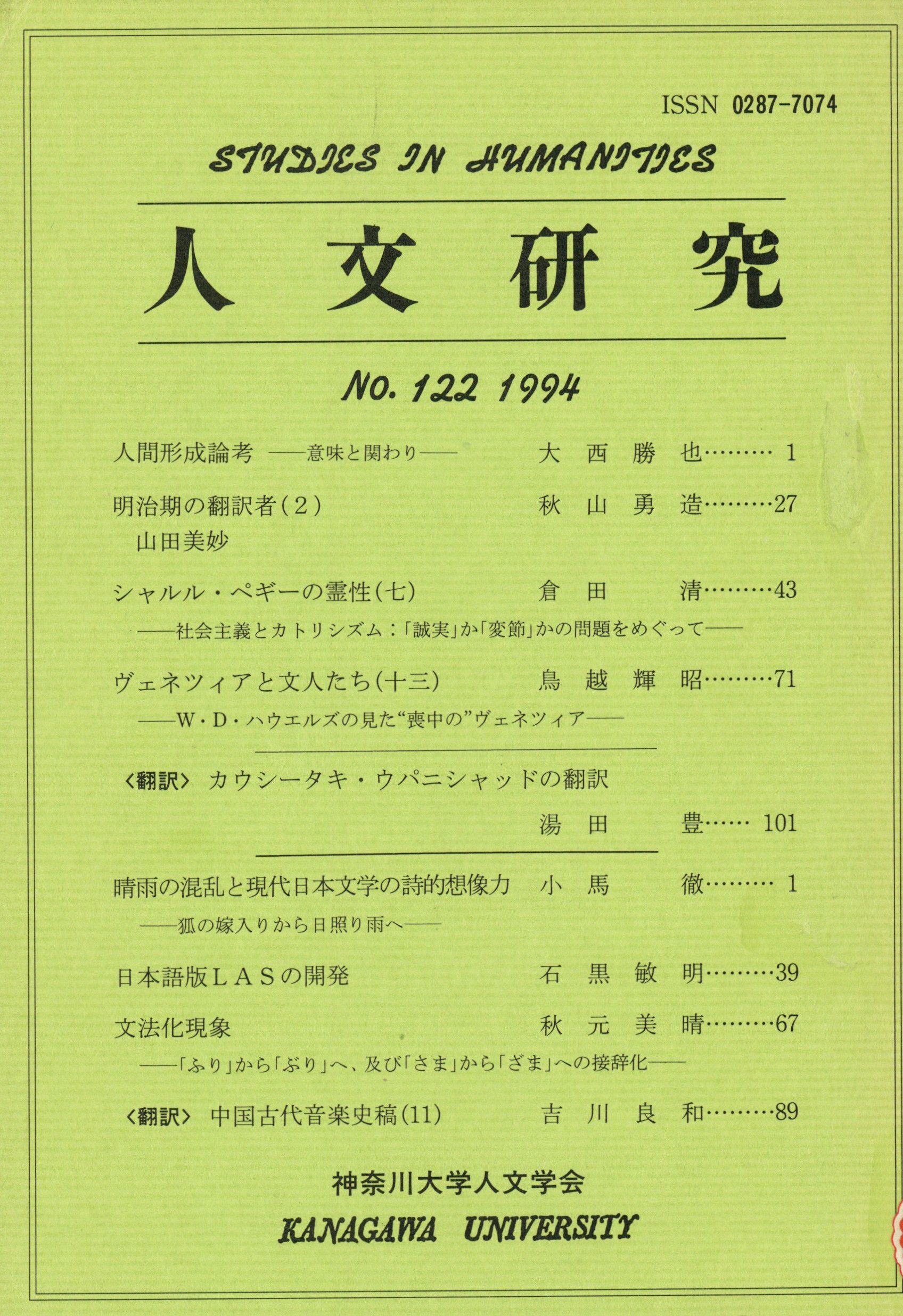
- 人間形成論考-意味と関わり-大西 勝也
- 明治期の翻訳者(2)山田美妙秋山 勇造
- シャルル・ペギーの霊性(七)
-社会主義とカトリシズム:「誠実」か「変節」かの問題をめぐって-倉田 清 - ヴェネツィアと文人たち(十三)
-W・D・ハウエルズの見た”喪中の”ヴェネツィア-鳥越 輝昭 - <翻訳>カウシータキ・ウパニシャッドの翻訳湯田 豊
- 晴雨の混乱と現代日本文学の詩的想像力-狐の嫁入りから日照り雨へ-小馬 徹
- 日本語版LASの開発石黒 敏明
- 文法化現象-「ふり」から「ぶり」へ、及び「さま」から「ざま」への接辞化-秋元 美晴
- <翻訳>中国古代音楽史稿(11)吉川 良和
No.121
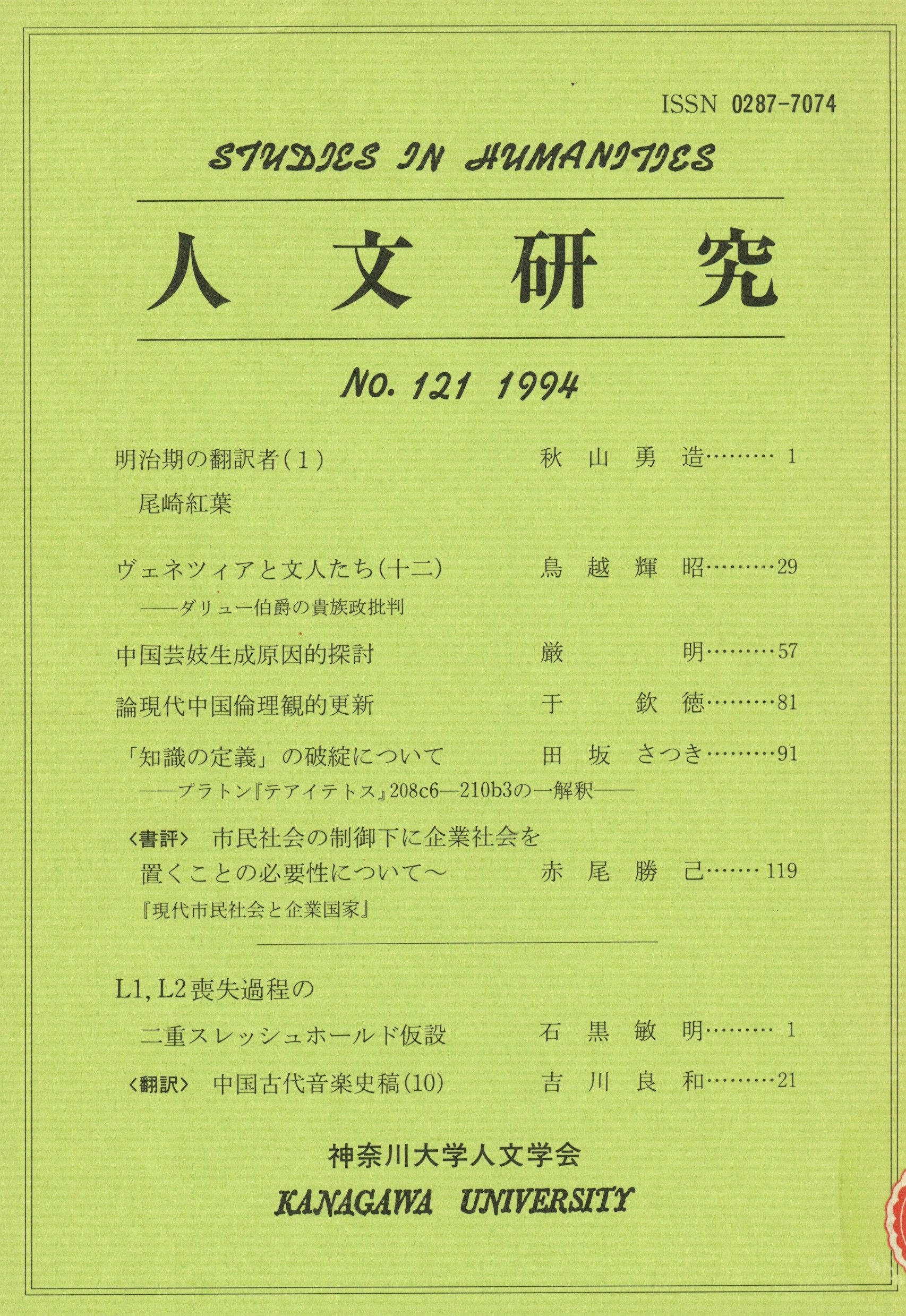
- 明治期の翻訳者(1)尾崎紅葉秋山 勇造
- ヴェネツィアと文人たち(十二)-ダリュー伯爵の貴族政批判鳥越 輝昭
- 中国芸妓生成原因的探討厳 明
- 論現代中国倫理観的更新于 欽徳
- 「知識の定義」の破綻について
-プラトン『テアイテトス』208C6-210b3の一解釈-田坂 さつき - <書評>市民社会の制御下に企業社会を置くことの必要性について~
『現代市民社会と企業国家』赤尾 勝己 - L1,L2喪失過程の二重スレッシュホールド仮説石黒 敏明
- <翻訳>中国古代音楽史稿(10)吉川 良和
